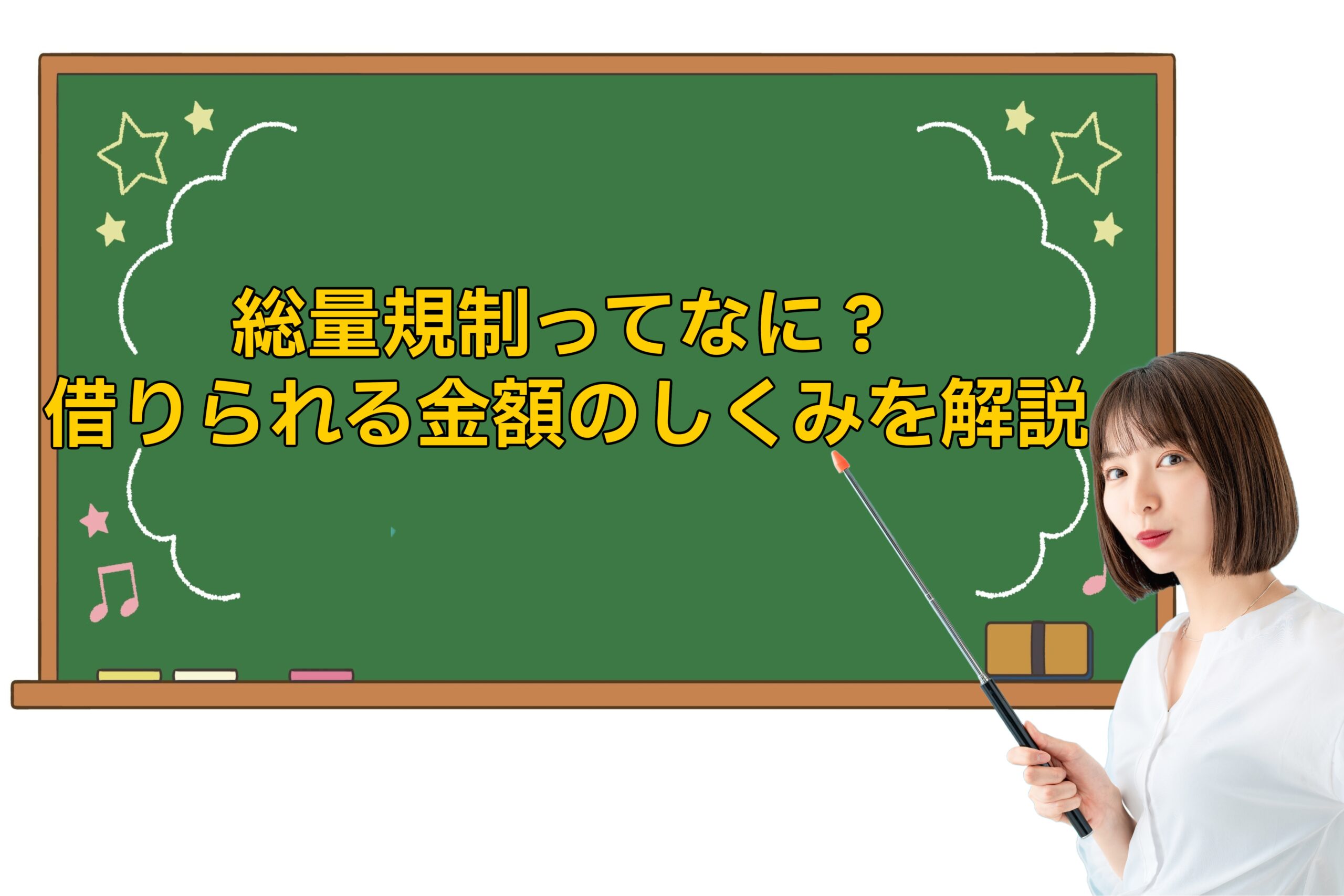
そもそも「総量規制」とは?
「総量規制」とは、個人の借りすぎを防ぐために導入された法律上のルールのひとつです。2006年の貸金業法改正により導入され、2010年に完全施行されました。この制度により、貸金業者(主に消費者金融など)は、借り手の年収の3分の1を超える貸付ができなくなっています。
たとえば、年収300万円の人であれば、消費者金融などから借りられる上限は100万円までということになります。これは、「生活に支障が出るような過剰な借入を防ぐこと」が目的です。
対象となる貸付と対象外のケース
ここで注意すべきなのは、「すべてのローンが総量規制の対象になるわけではない」という点です。総量規制が適用されるのは、主に貸金業法に基づく業者、つまり「消費者金融」「クレジットカードのキャッシング枠」などです。
一方、次のようなローンは総量規制の対象外です。
-
銀行カードローン
-
住宅ローン
-
自動車ローン
-
奨学金
-
リフォームローン(銀行系)
-
緊急医療費などの特別融資
-
配偶者貸付(一定条件あり)
そのため、「年収の3分の1を超えた借入は絶対にできない」というわけではなく、借り先や借入の目的によってルールが異なるということになります。
年収の確認方法は?必要な書類と注意点
総量規制があるということは、貸金業者は借入希望者の年収を確認しなければなりません。年収確認の手続きには、次のような書類が必要になります:
-
源泉徴収票
-
確定申告書(自営業など)
-
所得証明書(市区町村役場で発行)
-
給与明細書(直近2〜3ヶ月分)
これらを提出することで、業者は「この人にはいくらまで貸せるか」を判断します。また、すでに他社で借入をしている場合は、それも含めて合計額をチェックされるため、「自分では大丈夫」と思っていても審査で通らないこともあるのです。
専業主婦やアルバイト・年金受給者はどうなる?
年収のある方だけでなく、「収入がない」または「不安定な収入」の方も総量規制の影響を強く受けます。
専業主婦の場合:
総量規制により、配偶者の収入を証明できる場合に限って「配偶者貸付」という制度が利用できることがあります。ただし、この制度に対応している業者は限られており、必要書類も複雑なため、利用できるケースは限られています。
学生やアルバイトの場合:
アルバイトでも一定の収入があれば借入可能なケースはありますが、当然、限度額は少なめになります。安定性が重視されるため、勤続年数や雇用形態も重要な審査要素になります。
年金受給者の場合:
年金も「定期的な収入」として見なされることがあるため、年金証書などを使って借入ができるケースもあります。ただし、年齢による制限を設けている業者もあります。
総量規制を回避した貸しすぎへの懸念と現状
法律で定められた仕組みではあるものの、業者によっては「対象外のローン」を使って、結果的に借り手が多額の借入をしてしまうという事例もあり、社会問題化したこともあります。
特に問題視されたのは、「銀行カードローン」です。銀行は貸金業法ではなく、銀行法に基づいて営業しているため、総量規制の適用外です。そのため一時期、銀行カードローンでの過剰貸付が相次ぎました。現在では、銀行も自主規制を設けて総量規制に準じた運用を行うようになっています。
借入総額を確認する方法とは?
自分が今、どれだけの借入をしているか、把握していない人も少なくありません。そうした場合には、信用情報機関で「情報開示請求」をすることができます。
代表的な信用情報機関は以下の3つです:
-
CIC(株式会社シー・アイ・シー)
-
JICC(日本信用情報機構)
-
JBA(全国銀行個人信用情報センター)
これらの機関では、過去の借入や返済履歴、延滞情報なども記録されており、借入総額や借入件数を確認することが可能です。インターネットから申請でき、数百円で自分の情報を確認できます。
まとめ:借入は年収の範囲内で計画的に
総量規制は、無理のない返済を前提とした「生活を守る仕組み」といえます。ただし、「規制の枠をすり抜ければ借りられる」という考えは危険です。あくまで、自分の年収・支出に見合った金額を把握し、計画的に利用することが基本です。
また、複数の借入がある方は、いずれかのタイミングで「整理」「見直し」も視野に入れるべきです。無理のある借金は、将来的な信用にも大きな影響を与えます。
もし借入に不安を感じるようであれば、無理に申し込まず、家計の見直しや相談機関の利用も検討しましょう。制度を正しく理解することが、健全なローン利用の第一歩です。