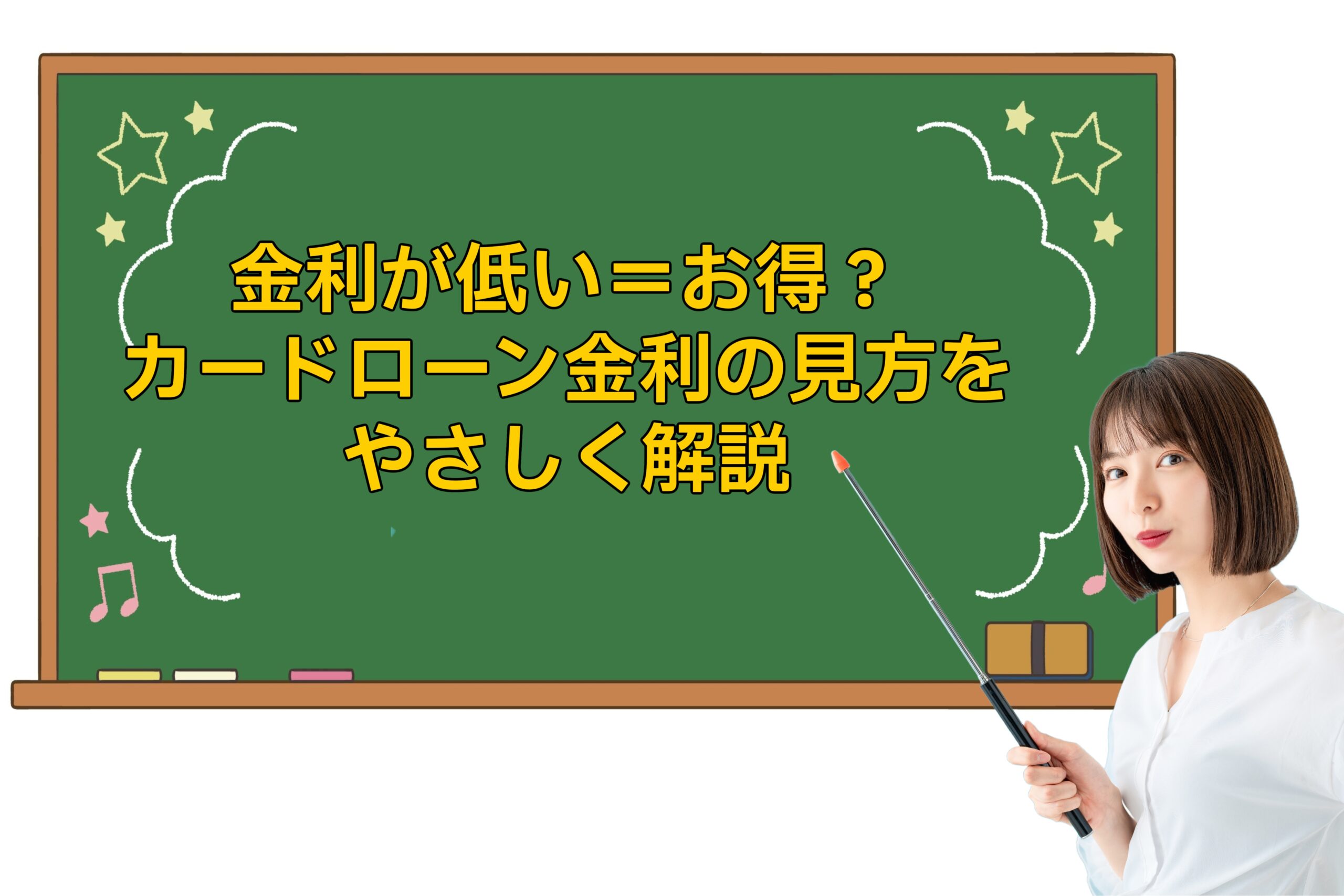
金利とは「借りるコスト」そのもの
「金利が低いカードローンを選びましょう」とよく言われますが、そもそも金利とは何でしょうか。金利とは、借りたお金に対して支払う利息の割合を示すもので、「年利」または「年率」という表記で示されるのが一般的です。
たとえば、年利15.0%のカードローンで10万円を1年間借りた場合、利息はおおよそ15,000円になります。つまり、返済時には元金の10万円に加え、利息15,000円を足した計115,000円を支払うことになるわけです。
このように、金利は「いくら借りて、いくら返すか」という借入の“総コスト”に直結する非常に重要な要素です。
金利の種類:実質年率と名目年率の違い
カードローンの金利表示でよく見かけるのが「実質年率」という言葉です。実質年率とは、単に利息だけでなく、「保証料」や「事務手数料」などを含めた“総コスト”を年単位で換算したものです。
一方で、名目年率はあくまで利息のみを基準にした金利であり、実際に発生する費用よりも低く見えてしまうことがあります。多くの金融機関では、実質年率での表示が義務づけられているため、申込者側としては「表示されている実質年率が、実際に支払うべきコスト」と理解して問題ありません。
金利は固定?変動?カードローンの場合は?
住宅ローンなどでは「固定金利」や「変動金利」がありますが、カードローンの金利はほとんどが「固定金利」に分類されます。ただし、固定といっても契約時点の金利であって、利用者によっては限度額や信用情報の変化に応じて後日引き上げられるケースもあります。
また、カードローンの広告には「年率3.0%〜18.0%」のように金利の幅が示されていることが多くあります。この場合、申込者の年収や信用状況、他社の借入状況などによって、実際に適用される金利は決定されます。
上限金利に注意!「最大値」が適用される人が多い理由
「最低金利3.0%ってすごくお得そう」と思うかもしれませんが、多くの利用者が適用されるのは「上限金利」のほうです。つまり「18.0%」のほうが実際に自分に適用される可能性が高いということです。
特に以下のようなケースでは、上限金利が設定されることがほとんどです:
-
初めてカードローンを利用する人
-
借入額が少額(10〜50万円程度)
-
年収が高くない/収入に波がある
-
他社の借入がすでにある
こうした理由から、「低金利」をうたう広告に飛びつく前に、実際にどの金利が適用されるかを確認する必要があります。
利息はどう計算される?日割りで計算される仕組み
カードローンの利息は、「元金 × 実質年率 ÷ 365(日) × 借入日数」という計算式で算出されます。
つまり、たとえば1日だけ借りてすぐに返済すれば、利息は1日分だけで済むのです。
これは「日割り計算」と呼ばれ、自由な返済が可能なカードローンのメリットの一つです。たとえば、10万円を年率15%で10日間借りた場合:
10万円 × 0.15 ÷ 365 × 10日 = 約410円
たった10日で返済できれば、わずか400円程度の利息で済みます。逆に、長く借りればその分だけ利息も増えるということです。
金利以外に見るべき「実質負担」
金利の数字だけで「このカードローンはお得だ」と判断するのは危険です。以下のような点もチェックしましょう:
-
返済方式:元利均等返済やリボルビング方式など、返済方式によっては返済総額に大きな差が出ることがあります。
-
手数料の有無:ATM利用料や繰上げ返済時の手数料がかかるかどうか。
-
最低返済額:毎月の最低返済額が少なすぎると、返済期間が長期化し利息負担が増します。
-
金利の引き下げ特典:利用実績によって段階的に金利が下がるサービスもあります。
これらを総合的に見ることで、本当に自分にとってメリットのあるカードローンかを判断できるようになります。
金利比較のポイントとまとめ
複数のカードローン商品を比較する際は、「金利の幅(最低〜最高)」だけでなく、自分がいくら借りるか・どれくらいの期間で返済するかを前提に考えることが大切です。
低金利ローンに申し込んでも実際に高金利が適用されてしまえば意味がありませんし、金利が低くても返済期間が長くなれば利息総額は増えてしまいます。
「金利を制する者が借入を制する」といっても過言ではありません。金利の仕組みを正しく理解し、借入時には冷静なシミュレーションを行いましょう。